兵庫県の市街化調整区域の場合、
「市街化調整区域 にある住宅が 活用しやすくなります – 兵庫県」>>
もチェックしてください。
緩和加速へ
神戸発 市街化調整区域の開発許可基準等の緩和例 R4.7.11~
農村地域での住宅の建築は、世帯分離(分家)や、市街化調整区域になった日(S45.12)以前から土地を所有している人等に限られていましたが、段階的に要件緩和を行うほか、共生ゾーン条例の里づくり計画に位置づけることで、都市住民による移住者用住宅の新築も可能になりました。
神戸市
また、空家の活用促進の観点から、使用者に制限のある農家住宅等を誰でも住める住宅にするための
基準緩和も行っています。
- 既存建築物の用途変更の対象を拡大・・・様々な用途に変更が可能
- 集落居住者の新築行為の対象を拡大・・・集落居住者が経営する一定規模の店舗・事務所等の新築が可能
- 日常利便施設の対象業種の拡大
- 市街化区域からの距離等を定めた立地要件の見直し
- 手続きの迅速化・簡素化
- 市街化調整区域での進入路基準の特例・・・進入道幅員3m~OK
- 「形の変更」の解釈基準緩和・・・一部開発許可不要に
- 市街化調整区域における開発行為の解釈基準緩和・・・区画・質の変更規模緩和

土地価格や固定資産税評価額が低く、都市計画税が不要である「市街化調整区域」で建築(新築・増改築)や用途変更の計画を進めるとき、厳しい「用途制限」の壁に当たります。(都市計画法(昭和43年6月公布)では「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする」とある)
現在の市街化調整区域で認められる建物例は、
1.農林業を営むものの居住の建物(農家住宅・農家分家住宅・農業用倉庫等)
2.市街化調整区域に居住している者の日常生活に必要な物販店、加工、修理等の業務を営む店舗、事業所の建物に限定されています。
市街化調整区域内での建築や用途変更の計画をする場合、農業を職業とする(新しく営農含む)ものとして住むか、上記2.に関連する事業を始める方法しかありまぜん。計画の施設等がそれらに当てはまるかの判断をまず市町村等の開発指導課で確認しましょう。
あいにく計画用途が不可とされた場合、最近は、「特別指定区域制度*」が創設され(通称「特区」)、兼用を含む一戸建住宅(農家でなくてもOK)を認める制度がありますので、まずは市町村へ「特区」指定の働きかけをすることからはじめないといけません。
*この制度は市町又は地域のまちづくりを行っているまちづくり団体等が、市街化調整区域の土地利用計画を策定し、この土地利用計画に基づき市町から申出がなされる区域を県が条例に基づき指定し、地域に必要な建築物を建築できるようにするものです。(兵庫県)
「特区」制度実現には時間は掛かりますが、公益的な意味で地域の活性化等に資する計画を後押しするのが行政です。
2025年が期限、市街化区域の生産緑地制度
一方市街化区域にある都市農家の税制優遇措置としてできたのが「生産緑地制度」。農地として活用すれば税金は優遇されるが、30年間売れない、貸せない、建てられません。全国で約4000万㎡ある生産緑地の期限が2025年。
2025年以降、都市農家は「宅地並課税」に耐えられなくなり、大量の土地が売り
出され、都市部の地価の暴落する減少が予想されます。
都市計画の基本を学ぶ本の紹介
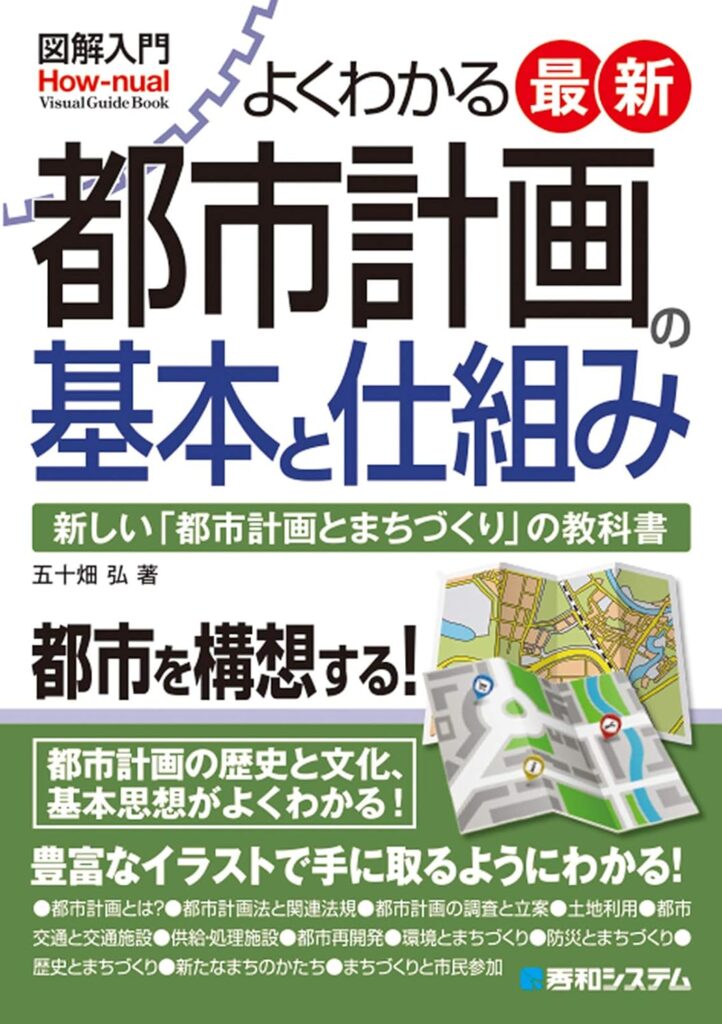
図解入門 よくわかる最新都市計画の基本と仕組み>>Amazon
2020/6/5
五十畑 弘 (著)
生産緑地はこう活用するQ&A――2022年問題に向き合う
– 2019/2/25
藤田 壮一郎 (著), 原 雅彦 (著), 中村 優 (著)
全国にある生産緑地の約80%(約1万ha)が指定解除の要件を満たす2022年に、多くの生産緑地が宅地化されることで社会問題化する「生産緑地2022年問題」。
特定生産緑地の指定を受けて、今後も営農を続けるか、新たに可能となった農家レストラン・農産物直売所の設置や生産緑地の賃貸を検討するか、2022年を待たずして着手可能な活用方法を探るか、買取り申出を行い土地の有効活用を目指すか、はたまたこれを機に手放すか……。2022年に向け、生産緑地の所有者には新たな可能性が示されるととともに、承継問題や相続など将来設計にかかわる重大な選択が迫られています。
本書は、基礎知識や税制、2022年に向けた選択肢、特定生産緑地の指定を受ける前に検討すべきこと、特別養護老人ホームへの活用など今できる生産緑地の活用方法、換地手法による生産緑地の有効活用、農地・宅地・買取り申し出後の生産緑地の活用例などについて、3人の専門家がアドバイス。
Amazon
