相談
これから文化財に登録申請しようとしております。寺院ということもあり、檀家さん一同、前向きに取り組んでおります。このような手続きが初めてのため、文章の作成などについて少し不安な思いをしております。
このような私共に何か言葉をかけていただけませんか?
答え
アドバイスとまで参りませんが、所見作成のことでしたら、もし、登録所見の参考になるものをご覧になったことがなければ、文化財課などで近隣の寺院の登録所見などを見せていただくこと。
なければ、兵庫県のものならこちらから入手ください↓
http://hyogoheritage.org/heritagenenpo/
ひょうごヘリテージ年報に登録申請の例(図面や所見)が多数掲載されています。ご参考にバックナンバー目次をご覧下さい。購入もできますよ。
地元の指定文化財の寺院の所見を調べてみること。(指定文化財:国宝、国の重要文化財、都道府県や市町村の指定文化財)
寺史等調査報告書の例>>『奈良県橿原市 浄楽寺 総合調査報告書』
指定説明(所見)は登録所見と基本的に同じですが、プロが書いています。できたら新しい所見のほうが現代的要件に沿っていて役に立ちますし、複数みると自分の好きな文体や表現にも出会えます。なかには図面をみなくても目に浮かぶような見事なものがあります。
文化庁のデータベースで同様な特徴のあると思われる文化財寺院を調べてその解説文を読んでみること。(地域、宗派、様式、時代など)↓
http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp
などでどのくらい書かねばならないかがわかります。ご自分でされるか、専門家に依頼されるのか、地元の文化財課の協力を仰ぐかにもよって違いますけれど・・・。
すでに必要書類・図面などのチェックリストやマニュアルはお手元におありでしょうか?なければ文化財課にきいてみて下さい。(県がよろしいかも)
登記は法務局、寺院明細帳が寺になければ図書館や宗派の上部組織等で寺史の一旦をたどることができるでしょう。
地誌はもちろん、寺宝や美術工芸品、仏像も専門家のアドバイスが必要になるかもしれません。市史や県史で地元の専門家をたどる、または地元文化財審議委員をたどりアドバイスをいただいてください。
取り急ぎ、思いついたことで失礼いたします。私もいつも、皆様のご指導受けながらやっております。お話聞かせていただければ、もう少しお役に立てるかもしれません。
意義深いことですので、どうぞ楽しみながらされてくださいますように。
日本木造遺産 千年の建築を旅する
– 2014/12/17
藤森 照信 (著), 藤塚 光政 (写真)
ユニークな建築史家・藤森照信氏と、建築写真のありようを変えた建築写真家・藤塚光政氏が日本中の個性的かつ風変わりな木造建築を訪ね歩いた紀行エッセイであり、日本木造建築のエッセンスを知る具体的なガイドにもなっています。
1. 浄土寺 浄土堂 2. 平等院 鳳凰堂 3. 錦帯橋 4. 松本城 5. 大瀧神社6. 奈良井宿・中村邸 7. 金峯山寺 蔵王堂 8. 旧金毘羅大芝居(金丸座) 9. 赤神神社 五社堂10. 臨春閣 11. 投入堂 12. 屋根付き橋 13. 蓮華王院 三十三間堂 14. 出雲大社 御本殿15. 笠森寺 観音堂 16. 成巽閣 17. 会津さざえ堂 18. 菅の船頭小屋 19. 富貴寺 大堂
20. 瑠璃光寺 五重塔 21. 坪川家住宅 22. 茶室 如庵 23. 嚴島神社 by amazon
日本木造遺産 千年の時を超える知恵
– 2024/6/8
藤森 照信 (著), 藤塚 光政 (写真)
それぞれの木造遺産について構造学の観点から、東京大学生産技術研究所の腰原教授がコラムを寄稿。
以下近畿のものを抜粋
01妙喜庵 茶室「待庵」 京都府乙訓郡大山崎町
06東大寺 南大門 奈良県奈良市
07東大寺 鐘楼 奈良県奈良市
16春日大社 御本殿 奈良県奈良市
17東山慈照寺 東求堂 京都府京都市
27箱木千年家 兵庫県神戸市
29高山寺 石水院 京都府京都市
30総本山 三井寺 光浄院客殿 滋賀県大津市
31法隆寺 西院伽藍と廻廊 奈良県生駒郡斑鳩町
32聴竹居 本屋と茶室 京都府乙訓郡大山崎町by amazon
ちなみに筆者がかかわった某県の寺院(近畿)の場合、「寺側の想い」以上に檀家のみならず地元(地縁者)で重要な建物であることが分かり、宗教だけでない地域の問題として自治体職員がかけつけていろいろ親身になって助けてくださいました。寺院では昨今、後継者、存続問題もある中、地域のこころの宝をまもることができ、近隣のかたがたにも喜んでいただけたことがありました。
ひとり檀家の某寺(四国)の場合は、文化在登録の要件に十分当てはまるにかかわらず逆に文化財化にこだわらないで寺の将来を考えた検証の仕方を考えておられます。文化財になったからといって継承問題が解決するわけではないので、寺とあれば檀家、寺を含む歴史共有している地域をまとめるひとつのきっかけにするというのも考え方のひとつです。
また早い段階で登録の費用を予算化すること、そして登録作業そのものをみなさんで共有しながら地域や寺の歴史をひもとくことが、登録後の寺院維持の力になることでしょう。
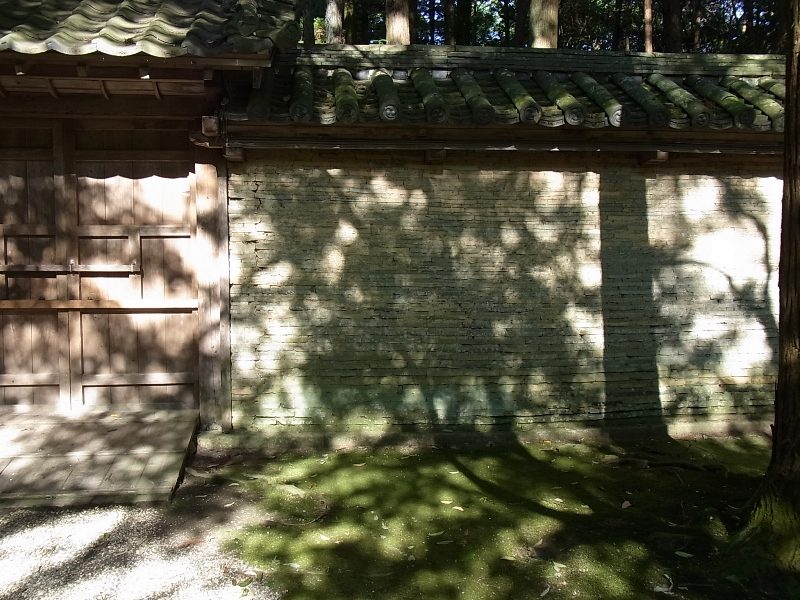
日本の美術 No 161 僧坊・方丈・庫裏 1979年10月号
服部 文雄
日本の美術 No 143 密教建築 1978年4月号
伊藤 延男
日本の歴史的建造物-社寺・城郭・近代建築の保存と活用 (中公新書 2633)
法隆寺や姫路城はじめ、日本には世界遺産に指定された歴史的建造物が多い。だが、役割を終えた古い建物でしかなかったそれらに価値や魅力が「発見」されたのは、実は近代以降のことである。保存や復元、再現にあたって問題となるのは、その建造物の「正しい」あり方である。歴史上何度も改築された法隆寺、コンクリート造りの名古屋城天守閣、東京駅、首里城……。明治時代から現代に至る美の発見のプロセスをたどる。
寺社建築の鑑賞基礎知識– 1992/9/1
濱島 正士 (著)
寺院や神社の建築は構造形式が複雑で様式手法が多彩であるため、鑑賞し、理解することが難しそうにみえる。美しいカラー写真や図を多く用いて、目で基本を理解できるようにした入門書。
図説社寺建築の彫刻: 東照宮に彫られた動植物– 1999/2/1
高藤 晴俊 (著)
近世社寺建築の白眉である日光東照宮の建築彫刻。その数多くの主題のうち、動物・鳥類・植物にわけて、それぞれの主題を特定する基準とした図像的特徴を紹介。理解を助けるイラストも多数収録。目の前の建築装飾を見る目がきっと変る、そんな一冊です。
2021~2024年調査した真宗寺院の調査報告書です。地域史、寺史、仏像、石仏、建築、宝物・什器に渡る調査を行いました。まったく民力でしたため、専門家のご協力といただいたご知見には脱帽いたします。

奈良県橿原市 浄楽寺 総合調査報告書 >>
2023年国の登録有形文化財、浄土真宗本願寺派
奈良盆地南部にある平坦集落にある中世からある寺院。
江戸時代に真宗寺院になり、廃仏毀釈で解体されていた多武峯妙楽寺の輪蔵(お経を納めた転輪蔵のための堂宇)を移築・改修して本堂として再建した数奇な寺院。
寺院調査に当たってこうした調査方法があることを広く知っていただくことで、地域の歴史や信仰の対象を見直し、識るきっかけになっていただけたらと思います。
