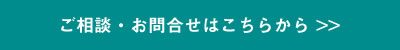登録文化財(建造物)は、1996年の文化財保護法改正により創設された制度で、2004年には民俗文化財、記念物も登録対象となりました。美術工芸品(古文書含む)もあります。

私は、2004年からヘリテージマネージャーとして活動を開始し、2023年まで奈良県で8件、兵庫県で8件、京都・山口・和歌山県で各1件登録文化財に関わってきました。また兵庫・奈良県の近代化遺産調査、兵庫・奈良・山口県の近代和風調査、国宝・重文建物の耐震基礎診断をはじめ耐震診断のための詳細調査、数件の文書調査にも参加させていただき「文化財の世界」の奥深さ・難しさを痛感しています。>>登録支援の例
こうした登録申請の実務や文化財調査の経験はきっと所有者の方のお役にたてるのでは、また私のみならず広く、多彩なヘリテージマネージャー仲間によるサポートも提案できるのではと思います。


登録文化財の候補になる建物は地域を代表する魅力のある建物が多く、地域の財産です。登録文化財制度がそれらを継承するための手助けになるよう祈りつつ、いつも調査・申請に取組んでいます。小さなことでも相談にのれたらうれしいです。>>ヘリテージマネージャーの実務
登録文化財申請の進め方
【1】相談
問い合わせフォームやメールまたはお電話でやりとりします。(簡単なやり取りは無料、リモート会議もOK)
【2】初期調査及び概要書の作成
現地にうかがいます。ある程度の判断、アドバイスがあればいたします。必要があれば、建物概要書を作成します。(調査着手前に見積をいたします)
【3】役所調整・スケジュールの確認(地元と及び文化庁スケジュール)
建物概要書をもとに、登録申請を担当する地元文化財課(市町村及び都道府県)と協議・調整をします。
実査する文化庁とのスケジュール調整も必要です(2024年~、実査は地元文化財課が実施)。
どこまでの調査、資料作成が必要かも判明します。
【4】現況調査
まずは行政サイドの現地調査時に必要な資料を作成します。(所有者情報、建物由緒、規模、改変歴、登録候補の範囲、今後の活用方針など)
登録文化財にするために必要な現況図作成のための実測と写真撮影をします。
また家の歴史や古文書の調査が必要な場合もあります。
地元文化財課の現地調査に立ち会います。
【5】申請書類の作成→申請
書類を作成しながら、適宜、文化財関係各課と内容について協議をします。
【6】文化庁の実査(2024年~、実査は地元文化財課が実施)
文化庁の調査官の実査を受け、質疑応答に対応します。再調査が必要な事象に関しては、調査を深めます。
【7】活用へ・・・活用者探しと公的支援
登録文化財となることで生まれるメリットをうまくいかしていきます。景観指定を受けたりまちの活性化のために役立てたりすることもできます。ひとつずつの建物のよさをひきだし、地域と連携することからはじめましょう。
また活用事業者探しのお手伝いや、登録文化財等への補助金調整も必要に応じ行いますので、ご要望をお聞かせくださいますように。
関連記事
登録文化財のメリット1 登録文化財のメリット2 登録文化財のデメリット・・・義務!と勧告!
ヘリテージマネージャーとは ヘリテージマネージャーいろいろ 京都市文化財マネージャー(建造物)
文化財登録のための図面作成 古文書調査の手引き 家と人、家系調べの方法
登録をゴールにせずに コロナ廃業 登録文化財「登録抹消」の増加
Q&A
補助
景観指定
法規
歴史的建造物の活用 2025「4号特例」廃止 2019「用途変更」200㎡~
問題と活用
本
市街化調整区域での民家活用-「こうべ茅葺トリセツ」2023改訂版も参考に
文化財の例
古景を閉じ込めた空間 多武峰旧真法院・旧慈門院、登録文化財に
【文化庁】令和6年度文化財建造物保存修理関係者等連絡協議会(第70回)